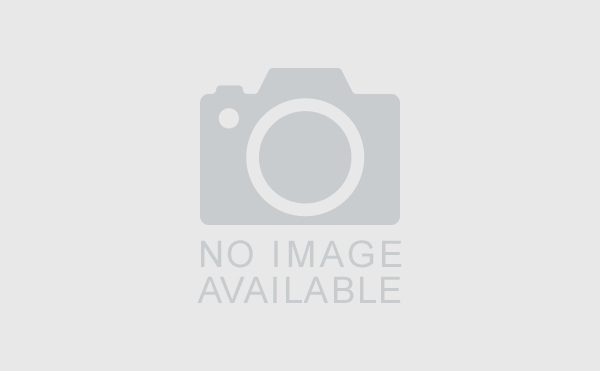新修亀岡市史 the Newly Revised Kameoka City History
はじめに
「丹の海」に関わる部分に関心がある。古本を探したが,新本販売中にもかかわらず送料を入れると新本の価格になってしまう。全く不要な資料編第3巻と,参考にはなるかもしれない資料編第5巻を「日本の古本屋」窓口から購入した。
亀岡市文化資料館で新本を購入するつもりだが,本文編第1巻,資料編第1巻,資料編第4巻,5,000×2 + 6,500 = 16,500円になるか。
昭和三十五〜四十年出版の『亀岡市史』上,中,下揃いと,昭和三十六年出版の『篠村史』(非売品)と,昭和六十年出版の『故郷鎮守の森 亀岡神社誌』も同窓口から購入した。いずれもリーズナブルな価格だ。まだ届かないが。
追記 2025年10月23日: 『亀岡市史』上,中,下,『篠村史』,資料編第3巻,資料編第5巻が昨日,届いた。『亀岡市史』上,中,下は明らかな盗難品で,上巻だけに残っていた所蔵機関の後継部局(京都歴史資料館)に電話したら,送らなくて良いという。中下巻の扉は見にくく破かれているが,この経緯を上巻の扉に示して,一応,使おうと思う。まあ,盗る方は悪いけど,盗られる方も問題ありだな。荒っぽい破り方からするとかなり大量に盗んだようだ。
1. 全8巻の内容紹介
驚くほど簡単な紹介だ。次の「2.各巻目次」が用意されているのは,2巻分だけ。
本文編第1巻 地理・考古・古代・中世前期 872頁
付録
- 亀岡市大字小字図(付図)
- 亀岡市大字小字図索引(冊子)
緑豊かな亀岡の自然環境の成り立ちを再検証。また、人々の営みを草創期から足利尊氏の挙兵までを叙述した通史編です。【平成7年1月刊行・第1回配本】
メモ:新本で購入することになるだろう,5000円(税込)
本文編第2巻 中世後期・近世 1,064頁
付録
- 近世の寺社と街道(付図)
- 大堰川筋絵図(復刻絵図)
- 南野山惣絵図(復刻絵図)
- 大井川筋立合芝原絵図(復刻絵図)
元弘3年(1333年)の足利尊氏の篠村八幡宮での旗揚げのころから、明治維新を目前にした慶応3年(1867年)の戊辰戦争前夜のころまでを対象とした通史編。【平成16年3月刊行・第7回配本】
本文編第3巻 近代・現代 1,080頁
付録
- 亀岡市域変遷図(付図)
- 小学校変遷図(冊子)
慶応4年(明治元年・1868年)から平成元年(1989年)までの、近代・現代の亀岡地域の歴史を叙述した通史編です。【平成17年7月刊行・第8回配本】
資料編第1巻 考古・古代・中世 1,448頁
付録
- 亀岡市の遺跡地図(付図)
- 亀岡市の遺跡(冊子)
考古では、市内で発掘された旧石器時代から江戸時代にわたる遺跡126カ所を図や写真で詳しく紹介し、古代では、丹波国全体を対象とした文献史料219点、木簡資料69点を収録、中世では、明智光秀が丹波入りする直前の天正2年(1574年)までの1,558点の文献史料を収録しました。【平成12年1月刊行・第4回配本】
メモ:新本で購入することになるだろう,5000円(税込)
資料編第2巻 近世 1,336頁
付図
- 丹州亀山城下町復原図/山陰丹府桑田亀山図/村落変遷図/形原松平系図
- 別冊 図版・亀山藩主一覧・明智光秀文書一覧・亀山城下町屋敷一覧
近世(江戸時代)の亀岡に関する史料を集めました。領主編・広域編・地域編にわけて、領主や亀山藩のことや、争論や水運・街道のこと、各村々の様子などを示す史料を多数掲載しました。【平成14年3月刊行・第6回配本】
資料編第3巻 近代・現代 1,326頁
付録
- グラフかめおか20世紀(写真集)
明治から平成までの近代・現代の亀岡に関する史料を集めました。本編は史料が中心ですので、「グラフかめおか20世紀」と題した写真集を付録としました。なつかしい写真がいっぱいです。【平成12年11月刊行・第5回配本】
メモ:古本で購入済み。
資料編第4巻 地域・文化財(建築・美術・民俗・地理) 1,042頁
付録
- CDブック『生活の中のメロディー~亀岡の伝承音楽~』
市内の寺社建築や仏像や美術品などを網羅。祭や年中行事など、ハレの民俗を収載。亀岡を航空写真と地形図の対比で知ることができます。都市地理的に重要な統計資料も収録。別冊としてCDに民謡や祭囃子などを収録しました。【平成8年3月刊行・第2回配本】
メモ:新本で購入することになるだろう,6500円(税込)
資料編第5巻 亀岡の民俗誌 1,230頁
市内の7地区の生活の様子を口頭伝承にこだわらず、生活史を語る文献史料も積極的に活用して詳細に叙述した民俗誌編と、亀岡祭の行列帳の翻刻や懸装品の一覧、方言の資料や、有形民俗文化財として梵鐘など埋け型の原型や民具、石造文化財などの一覧を収めた資料編で構成しています。【平成10年3月刊行・第3回配本】
メモ:古本で購入済み。
2. 各巻目次
一体,何が生じているのか,わからないが,各巻目次があるのは,本文編第1巻と資料編第三巻の二巻分だけだ。これはテキストで掲載する。他のコンテンツが無いので,画像データ(PDF)を掲載する。
本文編第一巻 目次
発刊のことば 谷口義久
監修のことば 上田正昭
序章 亀岡盆地の史脈と伝統 (2)
- 国境の第一国 (2)
丹波の亀岡/接点の要域/日本海とのつながり - 口丹波の軌跡 (8)
派遣の将軍/王権と古墳/律令制と丹波 - 変革と栄光 (16)
時代の変転/幕藩体制の亀岡/先人の活躍
第一章 亀岡の自然環境 (22)
第一節 亀岡市の位置と広さ (22)
- 相対的位置と絶対的位置/亀岡市域
第二節 亀岡の地質と構造 (26)
- 亀岡付近の地質と岩石 (26)
近畿の地質構造区分/亀岡の地質構造の分類/古い時代の地層/新しい時代の地層 - 亀岡付近の断層分布 (33)
主な活断層/亀岡断層・保津断層と西山断層/その他の断層/亀岡盆地の地下
第三節 亀岡市およびその周辺の地形概観 (42)
- 地形区分 (42)
接峰面図の作製/丹波山地 - 亀岡周辺の水系 (47)
市域を流れる河川/桂川水系/安威川水系と猪名川水系 - 亀岡付近の起伏の成立 (52)
- 丹波山地の起伏/亀岡盆地の推積層/亀の背地形(定高性)/古い時代の亀岡(第二瀬戸内海時代)/ブロック化/亀岡盆地の段丘地形
第四節 亀岡の地形誌 (61)
- 丹波山地 (61)
若丹山地/摂丹山地/盆地南側の山地 - 段丘と沖積平野 (70)
桂川左岸側の段丘/桂川右岸側の段丘/沖積平野 - 本梅盆地と谷底低地群 (76)
山地とその山麓/山麓の麓屑面/摂丹山地南麓の谷底平野群 - 特異な地形 (81)
谷中分水界/深い谷地形/曽我部町の地形/崩壊地形
第五節 自然と人間 (90)
- 集落 (90)
天井川と集落/山麓や丘段上の集落/沖積地と集落 - 災害 (94)
桂川の水災害/土砂災害 - 亀岡の気象 (99)
気候と降雨/霧の漂う盆地/寒天づくり
第二章 丹波の黎明 (108)
第一節 旧石器時代の丹波 (108)
- 旧石器時代の自然と気候 (108)
最初の住民/氷河時代/日本人はどこからきたか - 亀岡盆地の旧石器時代 (115)
鹿谷遺跡の石器/京都府域の旧石器遺跡/旧石器時代の生活
第二節 狩猟と採集の社会 (123)
- うつわの誕生 (123)
相次ぐ縄文遺跡の発見/土器の出現/縄文時代の時期区分/土器の編年作業/土器の年代 - 縄文土器の流れ (130)
縄文土器/草創期の土器/早期の土器/前期の土器/中期の土器/後期の土器/晩期の土器 - 縄文人のくらし (136)
住まい/縄文時代の人口/縄文人の行動範囲/貝塚/縄文人の墓 - 縄文人の道具 (142)
槍から弓矢へ/植物採集/魚貝類の採集/第二の道具
第三節 農耕社会の成立 (148)
- 稲作の伝来 (148)
太田遺跡の発見/稲の来た道/遠賀川式土器の広がり/稲作文化がもたらしたもの - 弥生土器の変遷 (154)
弥生土器/第一様式の土器/第二様式の土器/第三様式の土器/第四様式の土器/第五様式の土器 - 弥生ムラの実態 (159)亀岡盆地の弥生遺跡/環濠集落/最初の戦争/太田遺跡の石器/北金岐遺跡の田舟/大溝の堰/北金岐のムラ/北金岐ムラの交流
- 弥生人の墓とまつり (171)
犬の散歩でみつかった石剣/弥生時代の墓/弥生人のまつり/下弓削発見の銅鐸/銅鐸祭祀の終焉
第三章 古墳文化と古代豪族 (180)
第一節 古墳時代のはじまりと丹波 (180)
- 古墳の出現 (180)
園部町黒田古墳の発見/弥生の墳丘墓と古墳/倭王権の確立/古墳のひろがりと丹波/口丹波の初代首長 - 伝承からみた亀岡の古墳 (189)
口碑と古墳/桑下漫録と古墳/伝承からみた古墳 - 亀岡盆地の前期古墳 (194)
丹波への関門/丹波国と久我国/東アジアとの交流-筒形銅器 - ムラのくらしとまつり (200)
ベッドのある家/ムラの変化/木の容器/木でつくった鏃
第二節 前方後円墳の世界 (207)
- 倭の五王の時代 (207)
大王墓の移動/丹波政権 - 亀岡盆地の中期古墳 (210)
梅原末治の業績/棺と槨/副葬された鏡/丸い柱の家の埴輪/甲胄に身を包む被葬者/方墳の存在/地域勢力の動向/中期のムラ - 大王陵と千歳車塚古墳 (226)
江戸時代の千歳車塚古墳/千歳車塚古墳の復元/千歳車塚古墳と継体王朝/大王と丹波の盟主的首長
第三節 群集墳の展開 (234)
- 大陸文化の普及 (234)
横穴式石室の採用/六世紀の首長墓/横穴式石室の時代/新しい生産技術/装身具と機織り - 群集墳と村落 (251)
群集墳の形成/盆地各地の群集墳/石棚を持つ石室/古代のムラの風景/八木嶋遺跡と坊田古墳群
第四節 丹波と倭王権 (267)
- 古代の丹波 (267)
王権と古鏡/「丹波」の首長/丹波の県主/日本海と丹波/丹波王国論/丹波に居住した氏族 - 丹波をめぐる伝承と史実 (287)
后妃伝承/四道将軍/水江浦嶋子をめぐって/筒川嶋子伝説/常世の国/日下部首と嶋子伝承/豊宇賀能売命と大宮売命/櫛石窓神・豊石窓神/御食津神と丹波/倭彦王/千歳車塚古墳/蘇斯岐屯倉
第四章 律令体制の成立 (316)
第一節 古代寺院の成立 (316)
- 仏教伝来と地方伝播 (316)
古墳の終末と仏教/古墳から寺へ/丹波への広がり - 亀岡盆地の古代寺院 (322)
国府寺か/桑寺廃寺/瓦で化粧した基壇/ミコシ堂と塔ツカ/梵鐘をつくる/礎石が残る興能廃寺/寺院の空白地域を埋める/首長墓と古代寺院 - 古代寺院と氏族 (336)
屋根を飾る瓦/山陽道に分布する瓦/隼人と丹波の氏族/本薬師寺の瓦との共通性/藤原宮の瓦との共通性/高句麗系の瓦 - 寺院をみた民衆 (347)
竪穴から堀立柱へ/工人の村
第二節 国郡郷制度と農民生活 (350)
- 古代の亀岡 (350)
大化改新/律令体制/山陰道と丹波国/郷名の比定 - 丹波の居住者 (358)
丹波の豪族/秦氏/丹波氏/出雲氏/部民の系譜を引く氏族/隼人と蝦夷/土地制度と税制 - 丹波国の産業 (366)
木材/鉱工業/牧と氷室
第三節 丹波国府の造営 (370)
- 丹波国府の構造 (370)
丹波守大江匡衡/丹波国府の施設 - 丹波国府をめぐる諸説 (376)
桑田郡にあった丹波国府/丹波国府の諸説 - 丹波国府と発掘調査 (383)
池尻遺跡の発掘調査/千代川遺跡の発掘調査
第四節 国分寺と国分尼寺 (391)
- 仏教の伝来 (391)
国分寺建立の詔/仏教公伝/仏教興隆の主導権 - 国家仏教の成立 (395)
天武朝の仏教/神と仏/護国経典/神祗の体系化 - 僧尼の生産と統制 (399)
僧尼の生産/僧尼令 - 天平期の国家と仏教 (402)
行基集団/行基と光明皇后/天然とうの流行/玄ぼう - 国分寺・国分尼寺の性格 (408)
法華経と国分尼寺/光明皇后と阿倍内親王 - 丹波の仏教と国分寺 (411)
亀岡の古代寺院/丹波国分寺・国分尼寺 - 丹波国分僧寺を発掘する (414)
一七個の礎石/天にそびえる塔/再建された金堂/建物の配置/丹波国分尼寺はどこか/尼寺跡を掘る - 丹波国分寺の光と影 (423)
僧寺と尼寺/中央政府の技術指導/丹波国分寺と唐招提寺の瓦/如宝と空海/国分寺がたどった運命
第五節 古山陰道の変遷 (432)
- 奈良時代までの古山陰道 (432)
山陰道の要/国分寺と古山陰道/案察使/A-B古道の方位 - 平安時代の駅路 (440)
老ノ坂と大枝駅/野口駅・小野駅/国府への道
第六節 村落と条里 (446)
- 条里の制 (446)
古代の土地区画/坪並の方式 - 亀岡盆地の条里遺構 (450)
大堰川東岸の条里/古墳の立地/一致しない条里パターン/大堰川西岸の条里/犬飼川流域の条里/条里の分布限界 - 里の編成と集落 (467)
坪番号を示す小字名/坪並方式/文献資料の検討/墓廻里と車塚古墳/市域西端部の条里
第七節 仏教美術の伝播 (481)
- 天平時代の亀岡の仏教美術 (481)
金輪寺の薬師像/丹波康頼の伝承/甘露寺の十一面観音像 - 悔過信仰の流行 (487)
神護寺の薬師像/甘露寺観音像と悔過信仰/大宮神社の吉祥天像/市内の天平寺院
第五章 王朝の世界 (494)
第一節 山背遷都と丹波 (494)
- 丹波と長岡・平安遷都 (494)
平城京の放棄/丹波と宮都の伝統/造営の用材/宮都の労働力源 - 丹波医道の展開 (503)
平安時代の医学/丹波氏の伝統/丹波康頼と『医心方』 - 丹波農民の愁訴 (516)
愁訴とは/丹波国農民の場合
第二節 酒呑童子の伝説 (521)
- 酒呑童子説話の展開 (521)
説話の概要/二つの大江山/首塚/貴船の本地 - 老ノ坂子安地蔵の伝説 (535)
子安地蔵の縁起/子易物語 - その他の伝説 (543)
医王谷/千手寺縁起
第三節 生産技術の発達 (547)
- 丹波の古代の産業 (547)
現代に活きる古代の特産物/林産と木材加工/丹波の古代工業 - 篠窯跡群の成立 (554)
篠窯跡群の発掘調査/篠窯跡群の隆盛/西長尾三号窯/篠窯跡群の変換 - 篠の小型窯 (564)
小型窯の発見/小塩から篠へ/前山二・三号窯の発見/緑釉陶器/西長尾五・六号窯の発見/二つの相違した小型窯/窯で働いた人々/みつかった工房跡/篠製品の供給先/須恵器窯の終焉 - 平安建都・造寺と瓦生産 (578)瓦の歴史/丹波の瓦窯/篠瓦窯の操業/一号瓦窯はなぜ窖窯なのか/布目の瓦/平安京に運ばれた丹波の瓦/受領層と篠瓦窯
第四節 寺社の文化 (594)
- 穴太寺の信仰 (594)
平安時代丹波と仏教/穴太寺の創建 - 式内社の編成 (600)
神祗信仰の展開/式内社の成立/式内社の特質
第五節 仏教美術の光華 (609)
- 貞観彫刻の発展 (609)
平安遷都後の彫刻/兜跋毘沙門天 - 天台・真言両宗の進出 (613)
市内の天台宗寺院/市内の真言宗寺院/仁和寺領弥勒寺別院 - 穴太寺観音像の造立 (620)
仏師感世/都の仏師と在地の仏師
第六章 院政と源平の争乱 (626)
第一節 院政の成立と受領層 (626)
- 院政の確立 (626)
後三条天皇/白河院政の成立/受領層の活動 - 丹波守の特色 (631)
丹波の重要性/丹波守と院近臣 - 丹波守の活躍 (638)
源顕仲・季房/高階為章/藤原敦宗/藤原忠隆/国務の変遷
第二節 平氏政権と源平争乱 (648)
- 保元・平治の乱 (648)
保元の乱/平治の乱/丹波における武士団の出現/平治の乱と丹波の武士 - 平氏政権と源頼政の挙兵 (655)
平氏政権の成立/源頼政の挙兵/頼政塚の伝説 - 平氏の没落 (666)
丹波総下司の設置/平盛俊/平氏の都落ち - 源義経と亀岡 (672)
源平の合戦と丹波/義経の活躍/篠村の変転
第三節 仏教美術の発展 (680)
- 定朝様の流行 (680)
浄土信仰の広まり/寄木造法/仏師の組織 - 亀岡の定朝様仏像 (683)
おもな作品/釈迦像から薬師像へ/市内の院政期の仏像/市内の一木造像 - 亀岡の院政期の神像 (690)
神像とは/市内の神像/小幡神社と出雲大神宮の神像
第七章 公武政権の相克 (696)
第一節 幕府の成立と承久の乱 (696)
- 天下の草創 (696)
時政の上洛/地頭の設置/丹波守護大内惟義 - 後鳥羽院政 (704)
後鳥羽院政の成立/院知行国丹波 - 承久の乱 (710)
公武の対立/乱の勃発と丹波武士/京方の敗北
第二節 荘園と地頭 (719)
- 幕府勢力の浸透 (719)
乱後の情勢/六波羅探題と丹波守護/新補地頭の補任 - 中世荘園の成立 (726)
荘園・公領体制の成立/丹波における荘園 - 亀岡における荘園 (731)
摂関家領荘園/皇室領と御願寺領/寺社領の荘園 - 荘園をめぐる紛争 (740)
地頭の非法/地頭請と下地中分
第三節 鎌倉後期の丹波 (746)
- 政治・社会の変容 (746)
後嵯峨天皇の即位/幕府の変容と丹波守護/悪党の蜂起/一遍智真と穴太寺 - 足利高氏の挙兵 (757)
倒幕の気運/千種忠顕の上洛/挙兵以前の足利氏/篠村における挙兵
第四節 仏教美術の普及 (770)
- 鎌倉新様式の仏像の出現 (770)
慶派の進出/南都復興と慶派/快慶と市内の安阿弥様仏像 - 亀岡の石造美術 (777)
市内の石仏/真神寺御正体 - 亀岡の鎌倉時代の仏画 (779)
残りにくい仏画/釈迦十六善神像と大般若経
第五節 鎌倉時代の建築文化 (783)
- 寺院建築と石造層塔 (783)
絵巻に見る穴太寺/石造層塔/野口荘と神尾寺文化圏/古渓山千軒寺跡 - 広峯神社の棟札をめぐって (795)
棟札とは/樫舟神社と広峯神社の棟札/大梵天王/広峯神社本殿 - 愛宕神社の本殿 (803)
鎌倉時代の神社本殿遺構/新様式の摂取/「むら」の社
略年表 (810)
巻末資料
- 編さん委員・専門委員一覧
- 執筆分担一覧
- 写真・図・表一覧
- 参考文献一覧
付録
- 付図 亀岡市大字小字図(全三葉)
- 冊子 亀岡市大字小字図索引
本文編第二巻 目次
ブラザー複合機で性能はあまり宜しくなく,本をまずは紙コピーして,それを600dpiで給紙スキャンした。
資料編第一巻 目次
資料編第三巻 目次
『グラフかめおか20世紀』目次
刊行のことば 田中 英夫
監修のことば 上田 正昭
近代
一 史料解説 (3)
二 亀岡の明治維新 (16)
- 一 廃藩置県と新しい行政 (16)
- 二 立憲国家形成期の亀岡 (34)
自治の伝統と議会制度の導入/自由民権運動/弓箭組/村の生活/士族の状態 - 三 地租改正と諸産業の展開 (63)
地租改正/物産取調/小作問題/物産会の開催/土地取引/農村金融/銀行/鉱業/同業組合/社倉米/災害 - 四 近代教育制度と地域社会 (87)
教育行財政・初等教育/補習・中等教育・教員/明治初年の被差別部落の状況/地域・保津川下り
三 亀岡の近代化と再興 (140)
- 一 町村制の施行と新町村の発足 (140)
議会制度と近代化/町村の行政と状況/軍事援護/寅天堰と水管理/鉄道建設/弓箭組/村の生活 - 二 地主制の発達と諸産業 (205)
農業改良の進展/農業諸団体/米穀検査の開始/小作問題/農村金融/諸産業の発展/鉱業の展開/部落有財産統一/災害 - 三 学校教育の発達と地域社会 (241)
教育行財政・初等教育・中等教育/実業補習学校・夜学・青年会/教員・社会教育・壮丁教育/宗教・社会事業・婦人会/地域・保津川下り
四 第一次大戦と亀岡の発達 (288)
- 一 大正デモクラシーと地域の発達 (288)
一般行政など/諸団体/篠村部落有財産統一/亀能鉄道/寅天堰関係 - 二 農業の変貌と農民運動の展開(326)
商工業の発展/農業諸団体の発展/金融恐慌/土地改良事業の進展/京都府産米の声価/小作問題/自作農創設維持事業 - 三 教育の自由化と地域社会(362)
教育行財政・初等・中等教育/社会教育・教員・青年団・壮丁教育/宗教・社会事業・婦人会/地域・保津川下り
五 昭和恐慌と戦争への道 (408)
- 一 昭和恐慌と産業構造の変貌(408)
昭和恐慌期の農業/経済更正計画/自作農創設維持/地方銀行の整理・集中/小作問題/労働争議 - 二 昭和初期の町村行政(434)
一般行政など/軍事/旭村・富本村合併問題/河原林村・千歳村・馬路村合併問題/寅天堰問題 - 三 戦時体制下の行政・産業(460)
戦時農業/産業組合による病院経営/軍事援護活動/勤労動員/兵士・満州開拓民/医療・厚生/国民統制/官製国民運動団体/疎開・防空 - 四 昭和恐慌後の教育と地域社会(513)
初等・中等教育/社会教育・青年・教員/宗教・社会事業・地域
六 総記 (550)
- 一 日記(550)
山田理助日記/山田理一郎日記/山田晋太郎日記 - 二 政治関係書簡(671)
現代
一 史料解説 (685)
二 戦後亀岡の再出発 (694)
- 一 戦後の政治改革と町村政(694)
敗戦直後のようす/町村政の動向/警察と消防 - 二 戦後の暮らしと経済(744)
敗戦直後の生活事情/農地改革/農協の設立と農林業の発展/商工業の発達/世相・観光・文化/交通・通信・運輸 - 三 戦後の教育改革(796)
- 四 戦後の災害と復旧(820)
阿久根台風/デラ台風・ヘスター台風/ジェーン台風/七・一一水害/ダイナ台風と昭和二十七年の豪雨被害/昭和二十八年の災害
三 亀岡市の誕生 (902)
- 一 合併推進の動向(902)
旭村と船井郡富本村との境界変更/合併の促進/亀岡市の設置/合併前後のようす - 二 亀岡市発足後の合併(926)
昭和三十年代の合併状況/南桑田郡樫田村と高槻市との合併/亀岡市と船井郡東本梅村との合併/亀岡市東本梅町南大谷・若森と船井郡園部町との合併/西別院町牧・寺田の分市/篠村の合併/馬路町の一部の八木町への編入
四 新たな発展と亀岡市 (982)
- 一 亀岡市行政の展開(982)
市政の始動/選挙/行・財政/庁舎建設と公共施設/生活基盤の整備/道路・交通網 - 二 産業の発展と構造変化(1015)
暮らしの変容/住宅開発/工場誘致/農林業と伝統産業/商店街と大型店/観光/環境問題 - 三 災害と事故(1066)
水害とその対策/事故 - 四 住みよい町づくり(1096)
総合計画と公共施設/生活基盤の整備/人権・同和問題の取り組み/道路・交通網 - 五 教育と文化の発展(1141)
教育/文化 - 六 二十一世紀に向かって(1181)
市民憲章と宣言/姉妹都市と国際交流
統計資料 (巻末から)
- 人口(3)
- 財政(6)
- 公務員(12)
- 農林水産業(13)
- 事業所(38)
- 運輸・通信(47)
- 衛生(48)
- 教育・文化(49)
巻末資料
- 編さん委員・専門委員一覧
- 執筆分担一覧
- 資料提供・協力者一覧
- 写真・図・表一覧
付録
資料編第五巻
3. 詐欺サイト
「あなたが」という詐欺サイトにひっかった。埼玉県の詳細な住所や電話番号などがあり,この情報には疑いを持たなかった。新修亀岡市史全8巻が6,500円弱。
以前,祖父の遺品として1万円余でメルカリで販売されていたが今はもう購入済みであることは知っていた。写真も全く一緒。横流しなどの盗品であってもいいかなあ?と悪魔が囁く。下の図の個数の枠に誤って2を入れても全然問題がないことで奇妙に感じたことが良かった。
Perplexityに聞いたら,全くの詐欺サイトで,この「あなたが」の被害報告があるとのこと。口コミは中国のもの。会員登録をしてしまったので,悪用される可能性があり心配だ。
改めて,「日本の古本屋」サイトはツクヅク安心だと思う。ここでも新本販売中なのに,それより高かったりしている古本店はあるのだが。

以上,2025年10月21日。